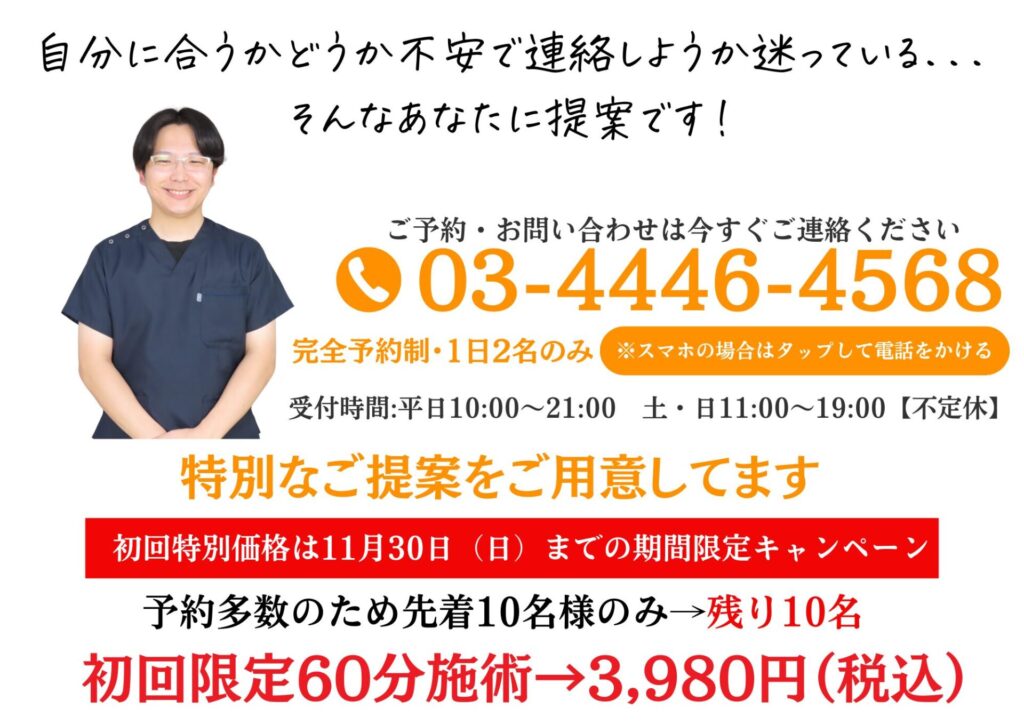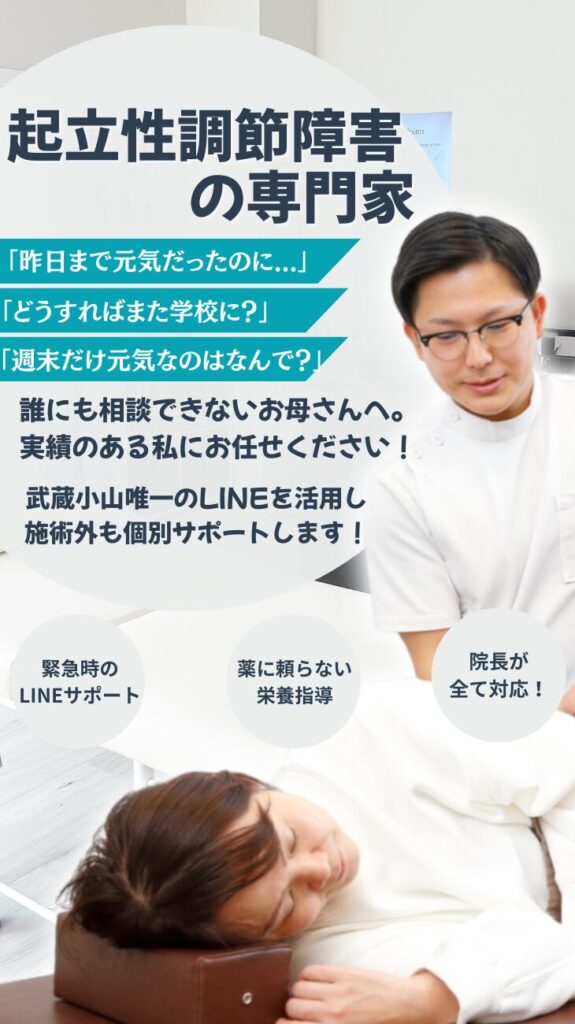
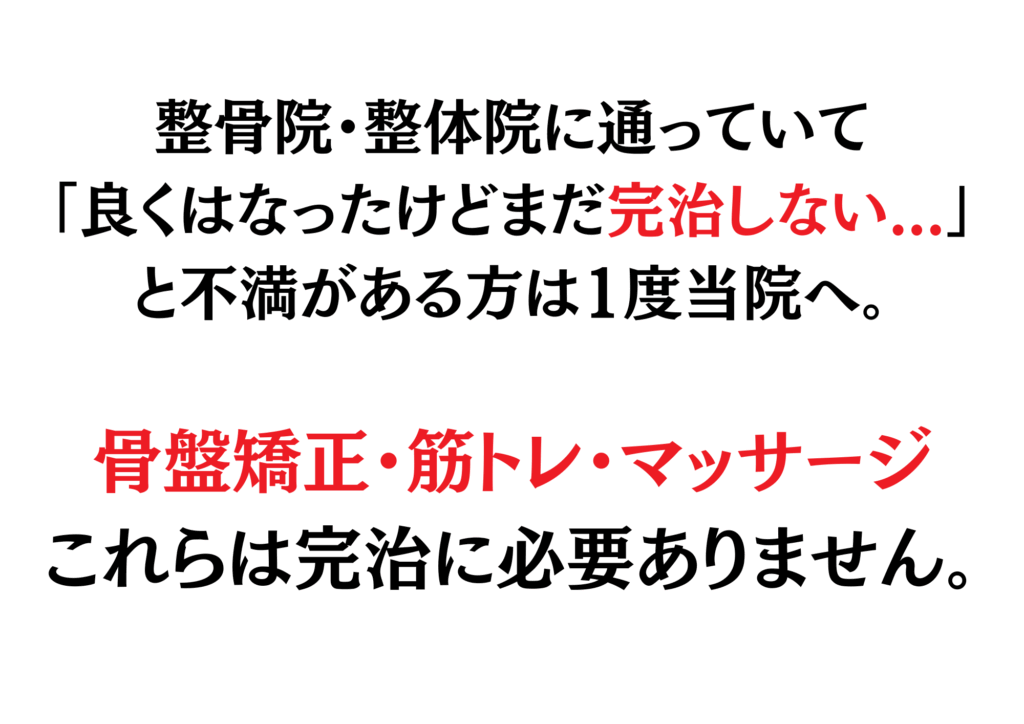
なぜ治らないのか?
当院の考えは以下の内容です。
ぜひ、一度目を通してください。
①ホルモンバランスの問題
起立性障害の発症時期が12~15歳くらいの場合、ホルモンバランスの問題を考えておかなければいけません。
ホルモンバランスというと、起立性調節障害でよく言われるのは副腎疲労ですが、そんなことの前に重要なのは性ホルモンの問題です。
2次性徴に伴い、男の子はテストステロン、女の子はエストロゲンなどの性ホルモンの分泌量が飛躍的に高まります。それ自体は必要なことで問題はないのですが、問題は増えたホルモン量に対して不要となったホルモンを分解するための肝機能がついていかない子がいるということです。
思春期の肝臓解毒機能は、増加したホルモン量に対して十分な解毒機能を持ちません。
薬やホルモンの肝臓代謝は、薬の種類やホルモンによって代謝経路が異なりますが、体内で不要となったホルモンは、肝臓で解毒され体外へ排泄されるまでは、中間代謝物(アルコール代謝でいえばアセトアルデヒド)として体内に残ります。
結果として、毒性の強い中間代謝物が体内で増え、頭痛やめまい、吐き気を引き起こします。
このような状態は、腸内環境の悪化による毒素の吸収↑、鎮痛剤などの薬物の使用、体に合わない食べ物の摂取などでさらに症状が悪化します。
当院の独自の検査をすると、解毒代謝を促進させる栄養素がわかり、合ったものを提案して摂ってもらうと、症状の改善がみられることがよくあります。
したがって、安易に症状の改善を求めて薬を飲むと、持っている問題によってはその場では症状が消えても、薬の効果が切れると症状が増悪することが考えられますので、安易に薬に頼るのは考え物です。
長く起立性障害を患っている方ほど、そういう悪いスパイラルにはまっていることがありますので、気をつけてる必要があります。
②脱水による問題
起立性調節障害ということで来院される方が増える時期は、9月~10月が一つの時期になります。
この時期に来なくても、症状を発症した時期がこの時期でいろいろ医者に行って、冬になってからうちに来るという方もよくいます。
来院された方々に、施術に際してカウンセリングをすると、「夏休み中に部活動を頑張った。その際熱中症やそれになりかけた」ということをよく聞きます。体感的には8割くらいです。中には、複数回熱中症になりかけたということも聞きます。
このような方々に、当院のある検査をすると、ほぼ100%の割合で脱水の問題を持っています。
この際に出てくる脱水は、水を飲む・塩を取るというだけでは済まないものであることが多いのですが、そういう方々に限って保護者の方が「水は2リットル飲ませるようにしています」という苦行を子供に強いていたりします。
体内に水を保水させるには、塩分が必須なのですが、しっかりと身体に水分を保水させるには塩分と同時に細胞そのものに保水するだけの能力があるかどうかを検査して、なければ保水できるようにしてあげないといけません。
たとえるならば、しっかりと樹木が茂り根を張った山と、土砂が露出したはげ山、どちらが水を保水できるのか?ということです。
はげ山状態の細胞に、水を取ったり塩分をとっても、全部流れ出てしまいます。
起立性調節障害(OD)の方々は、このようなはげ山状態であることが多いのです。
ですので、起立性調節障害(OD)を改善したければ、脱水の状態がないかをきちんと調べて対応をしてから、他の事をしていく必要があります。
③ミトコンドリアの代謝問題
ミトコンドリアというのは、人間の細胞内に存在していて、基本的に糖分を元にATPという人間を動かすのに必要なエネルギーを作り出しているものです。
これの働きが不十分になると、体を動かすエネルギーが不足し、体がだるくなったり、胃腸の不調などが現れてきます。
ミトコンドリアの機能を低下させる要因として、過剰な体内の活性酸素、脱水、酸素不足、糖分の摂りすぎ、ビタミンB1・B5の不足などがあります。
また、甲状腺機能が低下したり、副腎機能が低下してもミトコンドリアに問題が出ますが、逆にミトコンドリアの問題が、甲状腺や副腎に問題を引き起こすこともあります。
ミトコンドリアの問題は、とにかく全身に問題が出るので、起立性調節障害だけでなく、よくわからない不調を持っている方は一度疑ってもよい項目でもあります。
④交感神経及び副交感神経の問題
一般的に起立性調節障害においては、交感神経が過剰に働くことによって睡眠障害などが起こるとされています。
ただ、患者さんをみていると、交感神経と副交感神経の双方が過剰に反応しているケースもあり、一概に交感神経優位の問題だけとは言えないと思っています。
交感神経について書こうと思いますが、交感神経が過剰になる要因として、心理的なストレス・頸椎などの構造的な問題・栄養や代謝の問題などがあります。
心理的問題などありますが、長くなるため代謝や栄養の問題にフォーカスします。
よく見るのは、グルタミン酸の過剰やヒスタミンの過剰で、交感神経過剰状態や睡眠障害が引き起こされているケースです。
特にヒスタミンは過剰になると、頭痛や吐き気、皮膚の問題も引き起こします。
起立性調節障害を訴えて来院される方々の中には、吹き出物やアトピー肌を同時に症状としてあげられることがよくあります。
このような場合は、体内のヒスタミン過剰の問題を考える必要があります。
この問題を持っている場合は、いくつかの食品を一時的に除去したり、体内でヒスタミンやグルタミン酸を代謝できるような栄養を取っていただく必要があります。
人にもよりますが、持っている問題がこれだけだと、食品除去と2~3種類の栄養素を摂るだけで、起立性調節障害の症状が、きれいさっぱりなくなることもあります。
同じ起立性調節障害と診断されていても、有効な治療法が全く違うこともよくありますので、お子さんに合った治療が必要になります。
⑤心理的ストレスの問題
起立性調節障害を発症する子供たちの中には、心理的な問題を抱えていることが多くあります。
治療をしていく中で、最初は栄養的な問題などが、問題として大きく出ていても、それらが解消してきたとたんに、心理的な問題が浮かび上がってくることがよくあります。
特に中途覚醒があるような子の場合、顕在意識上及び潜在意識下で、常に問題のことを考えていて脳が興奮状態に置かれています。
興奮状態が静まらないから、寝付けないor途中で起きてしまう(眠りが浅い)ということになっているわけです。
心理的な問題を抱えている場合、まず考えなければいけないのは、”どんな問題が障害になっているのかを把握する”ことです。
これは、学校がかかわっていることもありますし、学校ではなく家庭内の問題ということもあります。
今まであった問題としては、
・夫婦仲の問題
・学校でのいじめ(現在もしくは過去)
・教師の態度
・勉強が思うようにできない(わからなさ過ぎて)のがストレス
・そもそも学校に希望や目的が持てない
etc….
いろいろな種類の心理的問題があるにもかかわらず、ただ学校生活についてのカウンセリングを行っても問題は解消されません。
(カウンセリングが意味がないと言っているわけではありません。カウンセリングのテーマの問題です)
また、心理的問題を解消するにあたっては、本人の協力(やる気)が重要になります。
わかりやすく言うと、「ストレスある?」という問いかけに「ない!」と言われてしまうと、どうしようもありません。
治療の回数を重ねれば、そのあたりも解消されていくこともありますが、初回で心理の問題があり、本人が非協力的だと、長丁場を覚悟していただく必要があります。
起立性調節障害を解消するためには、特定の分野だけ(身体の矯正・栄養療法・心理カウンセリング・ヒーリング等々)では難しいなというのが個人的な見解です。
その辺も踏まえ、目的をもって腰を据えて治療の術を探して、症状の改善を目指してもらえたらなと思います。
実際に同じ考え・施術で完治した方を一部紹介します。
このような考えを持った先生の施術を受けていますか?
長くなりましたが、多くの起立性調節障害の患者さんを見てきていますが「揉まれるだけ」「矯正されるだけ」「なんとなく自律神経の施術でお腹を揉まれた」という方が多いです。
それで完治すれば良いですが、このページを見ているということは、完治はしていないということです。
当院では、施術だけでは完治することが難しいと考えています。そのため何かあった時などにすぐ対策できるように「LINE」を使って相談を受ける体制をとっています。
子供であれば、学校行事がたくさんあります。また、部活などもしたくてもできない子もいます。
この時期は「時間」が1番大切です。
こちらもその時間を1秒でも無駄にしないように、責任もってサポートします。
本気で起立性調節障害をなんとかしたいという方はLINEで問い合わせください。